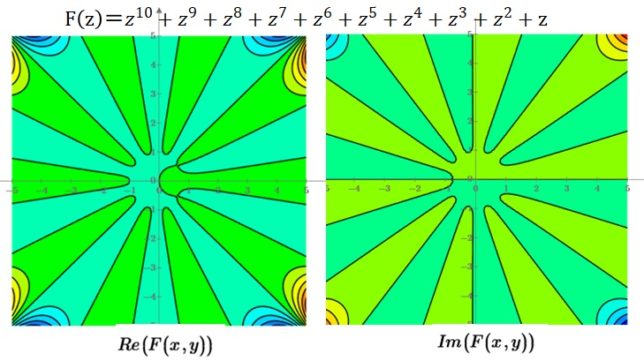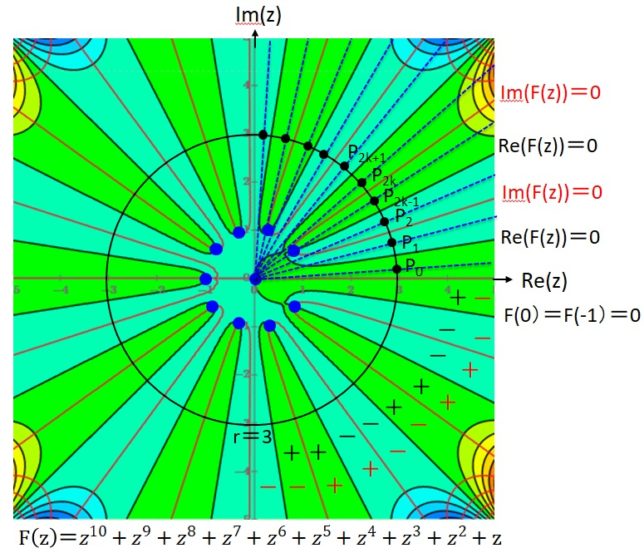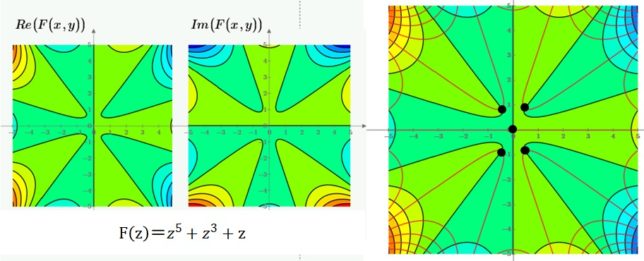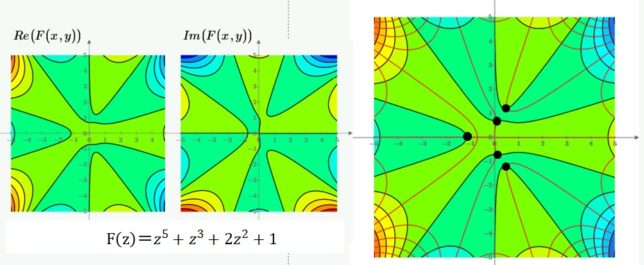4次方程式を題材にしてガロア理論を紹介します。
<フェラ-リの4次方程式の解法>
4次方程式は、平行移動で3次の項を消去できるので、一般にp,q,r∊Q[有理数]を用いて
- x4+px2+qx+r=0 ・・・(A1)
と書き表せます。両辺に2kx2+k2を付け加え、4次の項を平方完成させると
- x4+2kx2+k2=(2k-p)x2-qx
- (x2+k) 2=(2k-p)(x-q/2(2k-p))2+k2-r-q2/ 4(2k-p)
- (x2+k) 2=(2k-p)(x-q/2(2k-p))2+D(k)/4(2k-p)
となります。ここで判別式を
- D(k)=(k2-r) (2k-p) -q2=2k3-pk2-2rk+pr=0 ・・・(A1)
としました。この3次方程式を解いて、解kを代入すると
・(x2+k) 2=(2k-p)(x-q/2(2k-p))2
を得ます。ここで
- m=√(2k-p)、n=-q/[2√(2k-p)]
とおくと上式は
- (x2+k) 2-(mx+n) 2=0
- (x2+mx+k+n) (x2-mx+k-n) =0
より
- x2+mx+k+n=0
- x2-mx+k-n=0
と書けます。この2次方程式の判別式は、それぞれ
D1=m2-4k-4n
D2=m2-4k+4n
です。2つの2次方程式を解くと、結局4次方程式(A1)の解は
- x1=[-m+√(m2-4k-4n)]/2=[-m+√D1]/2
- x2=[+m-√(m2-4k+4n)]/2=[+m-√D2]/2
- x3=[-m-√(m2-4k-4n)]/2=[-m-√D1]/2
- x4=[+m+√(m2-4k+4n)]/2=[+m+√D2]/2
となります。ここで、k=k(p,r)は3次方程式
- 2k3-pk2-2rk+pr=0 ・・・(A2)
の解であり、
k-p/6=u(p,r)+v(p,r)、ωu +ω2v 、ω2u+ωv
m、nは
- m=√(2k(p,r)-p)、n=-q/[2√(2k(p,r)-p)]、
であります。
<4次方程式のガロア群>
3次方程式の解をu3,v3とすると、3次方程式の場合と同様に、有理数に1の三乗根を付加した固定体Qωを
- Qω⊂Qω[u]⊂Qω[u, u3]
と拡大することで3次方程式の解が得られます。さらに2つの判別式の項を加えて
- Qω⊂Qω[u3]⊂Qω[u, u3] ⊂Qω[u, u3, √D1]⊂Qω[u, u3, √D1, √D2]
と拡大することで、4つの4次方程式の解が得られます。Qω[u, u3, √D1, √D2]は固定体Qωのガロア拡大体です。5つの拡大体列に対応する5つのガロア群の縮小正規列は
・S4(対称群)⊃A4(交代群)⊃ B4⊃ C2 ⊃ E={I}
となります。A4はQω[u3]のガロア群、B4はQω[u,u3]のガロア群、C2はQω[u, u3, √D1] のガロア群です。それぞれの体と群の対応をガロア対応といいます。
n次方程式の解が四則演算と冪乗根で表せるガロア拡大体の数であるためには、ガロア拡大体に対応するガロア群の縮小列があって、全ての剰余群が巡回群でなければなりません。4次方程式の場合には上のようなガロア対応が成り立っており、全ての剰余群が巡回群なので、代数的に解くことができます。ガロア群の縮小列が形成できなければ、代数的に解くことはできません。
<4次方程式のガロア群の生成元>
解の入れ替えに関する写像は以下のI,J,K,L,Mの5通りです。J,K,L,Mは4次方程式のガロア群を生成する元です。
I:恒等写像 :(1234/1234)
J:u → v → u :(1234/2134)=(12)
K:u+v →ωu +ω2v →ω2u+ωv:(1234/2314)=(123)
L:(x1, x2, x3, x4)→(x4, x3, x2, x1) :(1234/4321)=(14)(23) ;(n,m)→(-n,-m) →(n,m)
M:(x1, x2, x3, x4)→(x3, x4, x1, x2) :(1234/3412)=(13)(24) : √ → -√ → √
- x1=[-m+√(m2-4k-4n)]/2=[-m+√D1]/2
- x2=[+m-√(m2-4k+4n)]/2=[+m-√D2]/2
- x3=[-m-√(m2-4k-4n)]/2=[-m-√D1]/2
- x4=[+m+√(m2-4k+4n)]/2=[+m+√D2]/2
4次方程式の4つの解の入れ替え写像は、2つの解の入れ替え写像の合成演算により、対称群S4をなします。4元の入れ替えは4!=24通りあります。まずはL、Mの演算について調べてみましょう。
LM=(1234/4321) (1234/3412)=(1234/4321)(4312/2143) =(1234/2143)=(12)(34)
つまり、LMは1⇔2、3⇔4の交換を行います。(x1, x2, x3, x4)の2組の互換は、M、L、LMの3つしかありません。
ML=(1234/3412) (1234/4321)=(1234/3412) (3412/2143)=(1234/2143)=(12)(34)=ML
MM=(1234/3412) (1234/3412)= (1234/3412) (3412/1234)=(1234/1234)=I
LL= (1234/4321) (1234/4321)=(1234/4321) (4321/1234)=(1234/1234)=I
なので
- B4={I、M、L、LM}
は群をなします。ML=LMなので、B4は可換群です。B4はJ,Kとは可換なので、S3の正規部分群になっています。またB4の全ての元は遇置換です。B4はQω[u, u3]のガロア群です。Qω[u, u3]によってkの値が固定されても、(x1, x2, x3, x4)は影響を受けません。B4の部分群について調べてみましょう。
- E={I}⊂ C2={I、M}⊂B4
C2はS3の正規部分群になっています。
LL=Iなので、剰余類B4/ C2は巡回群です。√D1の最小多項式の次数は2です。
- B4/ C2={I C2、L C2}
MM=Iなので、剰余類C2/Eは巡回群です。√D2の最小多項式の次数は2です。
- C2/E={EI、EM]}
対称群S4は、4!=24個の元からなり、
- S4=JA4∪I A4
- A4={I、K、K2}・{I、M、L、LM}={I、K、K2}・B4
- B4={I、L}・{I、M}={I、L}・C2
の様に分解できます。A4は12個の元からなる交代群(遇置換群)です。JA4は群ではありません。
A4={I、M、L、LM、、KI、KM、KL、KLM、、K2I、K2M、K2L、K2LM}
JA4={J、JM、JL、JLM、、JKI、JKM、JKL、JKLM、、JK2I、JK2M、JK2L、JK2LM}
剰余類S4/ A4は巡回群になっています。
- S4/ A4={I A4、JA4}
剰余類の要素の数を位数といいます。S4/ A4の位数は2です。剰余類の位数は、対応する代数体に加えた数の最小多項式の次数と一致します。補助方程式を解くためにu3(=√)をQωに加えたのですが、u3の最小多項式は2次なので、位数2と一致しています。
剰余類A4/ B4は、K B4=B4 Kなので、巡回群になっています。
- A4/ B4={I B4、K B4、K2 B4}
A4はQω[u,u3]のガロア群です。u3、v3からu、vを出すためにuを加えました。Uの最小多項式は3次なので、剰余類A4/ B4の位数3に対応しています。
以上、4次方程式を解いて、そのガロア群について調べてみました。4次方程式の解の入れ替えに関して縮小するガロア群の列が形成でき、その剰余類が一つの元から生成せれる巡回群だったので、4次方程式の場合はガロア拡大体に解を見出すことができることが確かめられました。